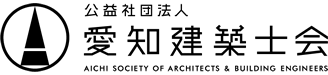愛知建築士会の活動
講演会 男女共同参画のこれまでとこれから に参加して ~なぜ「男性の家庭参画」が大切なのか~ 名古屋北支部 秋好大樹
2025-03-31女性委員会
男女共同参画―よく耳にする言葉ですが、実際にどれだけの男女差があるのかよく知らないため、
令和7年2月1日に女性委員会が開催した講演会に参加しました。
講師の田村哲樹氏は名古屋大学法学研究科の教授であり、名古屋大学の男性職員で初めて育児休業を取得された方で、
それは二人目のお子さんが生まれた翌年の2002年のことです。
男女共同参画社会基本法が1999年に施行されて間もない頃で、男性の育休取得率0.3%という時代。
育休取得率を2002年→2023年で比較すると、
女性49%→84%、男性0.3%→30%とかなり増加していますが、まだ男性の取得率は低い状況。
男性の育休取得の意識としては2002年当時で、70%が取得希望があったにも関わらず、実際の取得は0.3%ということです。
「男女共同参画」は、今までは「男女共同参画」=「女性の問題」として扱われることが多く、
「女性のチャレンジ支援、活躍促進」の施策が実施されてきました。
「女性のあり方」を変えようとしたといえます。
仕事を継続し活躍するための施策として「時短勤務や育児休業延長制度」が一般的になりましたが、
もっぱら女性だけがこの制度を選んでおり、これは「家事や育児は女性がやること」という状況を助長しており、
結局は女性がキャリアを諦めることに繋がっています。
「男女共同参画」の本当の問題は「家事や育児は男女関係なくやること」つまりは「男性のあり方」ということ。
2002年の育休取得希望70%に対して取得率が0.3%という点をみると
「男性が育児をするなんて」
と男性の家庭参画を特殊なものと社会が捉えていた表れといえるでしょう。
しかし在宅勤務が増えたコロナ禍の影響もあり2022年17%から2023年には30%と大幅増となっており、
社会の認識も変わってきているようです。とはいえまだ30%。
そこで私は田村先生に質問をしました。
「2002年当時でも70%の育休取得希望がありましたが、20年経っても取得率は30%です。何が障壁になっているのでしょうか?」
先生の回答としては
「まだ男性が家庭参画について世間の目を気にしているからではなかろうか。
社会を変えるためにも男性自らが声を上げ、行動していく必要がある」とのことでした。
また男性の家庭参画が増えているとはいえ「サポート」としてのスタンスが多く、
あくまで補助、手伝っているという意識を変えていかないと本当の「男女共同参画」には成りえません。
そのためには「話し合い」=熟議が大切。
「仕事と家庭のバランス」をどのように決定するか、
日本ではもっぱら母親が決めるべきことと考える人が多いのに対して、
アメリカでは夫婦で一緒にその決定をすべきものと考えている人が多いそうです。
家庭のことは誰かのことではなく自分ごととして向き合って、
そして「話し合える関係」になりお互いに納得できる「答え」を見つけることが重要であるというシンプルで深い言葉が印象的でした。
そのためのヒントとして
「相手への注文よりも、わたしはどうしたいか?を伝える」
「答えは、わたしとあなたのあいだにある」
「それぞれの思い・意向・こだわりをうまく手放すこと」
を意識すると良いそうです。
田村先生はお子さん二人を連れて2年間、キャンベラで「父子生活」をしたりと(奥様は仕事継続のため日本)、
率先して家庭参画されていて、一つ一つの言葉に重みがあると共に楽しそうにお話しされるお姿がとても印象的でした。
講演会の後には交流会・意見交換会もあり楽しく勉強になる講演会でした。